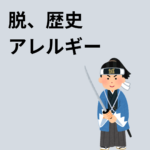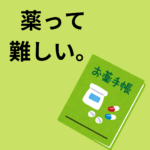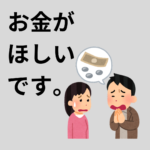こんにちは、くまねこです。今日は「ゼミの活動」について紹介したいと思います。大学でも教授ごとにゼミがあったりするので、実際にゼミに入っていた方はその時の活動をイメージするとわかりやすいと思います。
大学院のゼミでは、さらに狭く深く「専門分野の研究活動」をメインに行い、それを最終的には「修士論文」につなげる、といったことをしていきます。
最終的な目標はそこなのですが、内容やそのやり方はゼミによっても異なりますので、今回は実際に私が入っていたゼミや友人のゼミを参考にしつつ、体験談を紹介したいと思います。
1.私自身が所属していたゼミ
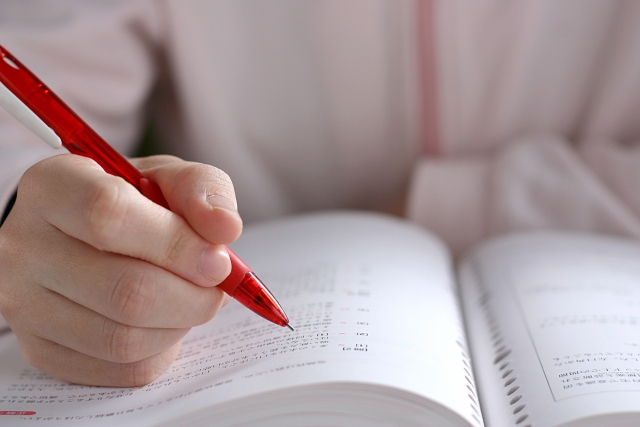
私が所属していたゼミは臨床心理学の中でも「医療系のゼミ」でM1,M2併せて大体8~10人くらいいました。
最終的な目標は修士論文なのですが、
そこへの準備として、その日ごとにゼミの先生が選んできた、もしくはゼミ生が自身の研究テーマと関連のある英語の論文を読んで、皆で議論し合うことをメインに活動していました。
例えば、ゼミの先生ががん患者への介入研究をしていたことから、患者への心理支援の介入に関する論文を読んだり、またゼミ生が統合失調症の研究をしていたことから、それに関するものを読んだりなど、「医療における臨床心理学」にまつわる様々なテーマを翻訳する機会がありました。
修士論文では、英語論文を引用することも必要になってくる可能性があるため、その前段階として、英語に慣れるという意味合いや、参考になる論文に触れるということが目的だったのだと思います。
また、その他にも学会発表をする機会も秋ごろにあるのですが、直前には発表内容をまとめて、ゼミ内でプレゼンしたりすることもありました。
(学会発表に関しては、また別の記事でご紹介させていただきますね^^)
そして、これらの活動はすべて、大学院修了の要件となる「修士論文」のクオリティにもつながっていきます。
修士論文で質の高い発表をしていくためにも、
これから入学をされる方は、なるべく英語に触れておく、ということも改めて意識してみると良いかもしれません^^
2.友人のゼミ活動

私の友人は別の先生のゼミに入っていたので、そちらも合わせて紹介しようと思います。また少し異なる活動もありますので、色々なゼミがあるということで参考にしてみてください^^
1つは主に発達心理学に関するゼミです。
学内の相談センターに来る子供たちの支援の結果をまとめて、ゼミ内で発表していることが印象的でした。
これらのデータで修士論文を書いた学生もいたはずです。
また、1から研究のテーマを決める人は倫理審査(その研究が倫理的に配慮されたものか審査する)を通すため、ゼミで議論するといったこともしていたようです。
他には、高齢者を対象とした研究をするゼミもありました。
このゼミは実際に大学に高齢者に来てもらって、そこで心理検査などを行い、約3,4年同じ高齢者を対象に研究を行っていました。いわゆる縦断研究というものです。
そのため、私の友人は、大学4年から高齢者のゼミに所属し、大学院入学後も引き続き同じゼミに所属して、長期間の研究成果を修士論文にまとめることを目的としていました。
以上をまとめると、ゼミ活動では「専門分野に関する研究や活動」を中心に行ない、最終的には修士論文につなげる、といったことをしているようです。
3.活動で大事にするといいこと

ゼミ活動を2年間やってみて、特に大切に思ったことは、やはり「準備」が非常に重要だ、ということです。
授業は多少受け身でも困りませんが、ゼミ活動では、行ったことがすべて最終的に「自分の修士論文」につながります。
なので、主体的に取り組まないと、
あわてて引用文献を収集する・・・
あわてて専門分野に関する勉強をする・・・
といったように終盤に切羽詰まってきやすいです^^;
具体的には、それぞれの研究の経過を発表したり、倫理審査の準備をする場もありますので、その都度次回のゼミに向けた準備をしっかりしたうえで臨むと安心でしょう。
ゼミ内では、学生同士や先生とディスカッションする場面もありますので、研究について色々意見をもらったら、忘れないうちに記録しておくと後々役立ちます。
さらに、ゼミでは先生と話せる絶好の機会でもあるので、分からないことや研究の進め方について聞きたいことがあれば積極的に聞くとよいです。
先生もなかなか忙しく、まとまった時間を作って質問しに行くのは難しいので、ゼミの時間を有効に使ってみると良いと思います。
このような形でゼミの活動についてまとめましたが、「専門分野の研究」にまつわる活動がメインとなりますので、授業よりも狭く深く、学問を探求する機会になると思います。
最初はこれだ!と思えないテーマであっても、勉強していくうち、やっていくうちに楽しくなっていくこともあると思います。(私は結構そうでした)
ぜひ、どんな分野でも、大学時代とは一味違う「狭く深く学問を探求する」という経験を味わってみてくださいね^^