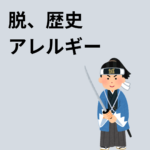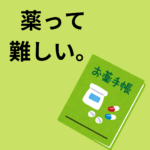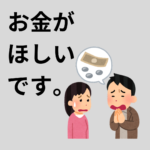皆さんこんにちは、くまねこです。
前回更新から長らくお待たせしてしまい、すみません。
ブログを楽しみに待っていてくださった方、いつも本当にありがとうございます。
2月を最後に更新できておらず、約6か月ぶりです。
久しぶりの更新なので、少し気合いれたテーマで書いていきたいなと考えてました。
(しかし、考えれば考えるほどハードルが上がってかけない^^;)
色々考えた末ですが、、、
今回は、臨床経験浅めの自分が壁にぶちあたりがちだった、「アセスメント」について書いていきたいなと思います。
今思い返すと、
大学院の実習生時代や、臨床経験1~2年目など、特にまだいろいろな経験や知識が統合されていない頃は、訳も分からず、とりあえずテキスト通りor先生の言うとおりにすすめていくしかありませんでした。
基本に忠実にやっていくしかないのは分かりつつも、なんとなく本質がつかめていない感覚も強く、基本的に迷走していたと思います^^;
その頃の自分を思い出しながら、現在どのようにアセスメントを行っているのか、少し書いてみようと思いました。
クリニックでの経験を多少なりともつんだことで、以前と比べると、より体験的に、感情的に、立体的に・・・?
うまい表現が見つかりませんが、患者に対する理解ができるようになってきたのかなと思います。
今回は、初回面接の流れというよりも、アセスメントに焦点を当てたいと思います。なので、初回面接で情報収集をした後、私が実際にクリニックなどでやっているアセスメントの視点を4つに絞って書いていきたいなと思います。
初学者の方にとって、なにがしか、アセスメントのコツをつかむきっかけになってくれればと思います。
(そういう私も、まだまだ勉強不足なので、このブログテーマもまた、随時書き直していくかもしれません^^!)
1.原家族を踏まえた理解
では早速・・・。4つのアセスメントの視点の1つ目、原家族を踏まえた理解、としました。
ひとそれぞれ、どこから視ていくか、は違うかもしれないのですが、
私の場合は、まずは患者自身や最も近い対人関係である家族に焦点をあてることで、患者さんの全体像がつかみやすくなると思っています。
具体的には、生活史や原家族の構成を聴いていくなかで、こういった部分は特に分かってくると思います。
(あのジェノグラムを書きながら、聞いていくヤツです←実習が始まっている学生さんはわかるかな^^)
そのなかでも、どういった情報でアセスメントしていくかというと・・・
特に原家族についてのお話は、重要です。
患者自身がどのような環境で生育してきたのか。家族構成や家庭内のパワーバランス、個々の関係性(母親と患者の関係、父親と患者の関係、母と父の関係、兄弟間の関係・・・など)を聴いていきます。
聴いていく中で、現在の患者自身の性格、考え、価値観ができあがってきた背景を理解していきます。
もちろん、患者自身の特性もあって、相互に影響しあって発達していくものだと思いますが。
そのなかで、程度の差はあれ、いろいろな家族の問題が見つかることも多いです(DV、過干渉など)。
そのような家庭で育った場合には、自立やアイデンティティの確立に必要ないろいろな経験が不足している場合も多いです
(人に適度に頼れない、自分の生活を主体的にコントロールできない、アサーションがうまくいかない・・・etc)。
家族のなかで培われたパターンが、患者の現在の問題ともリンクしてくるなぁと実感することは多いです。
こんな感じで、
基本的に対人関係のスキルは家庭内を基盤に身につくものなので、原家族の情報は重視して聞いていると思います。
2.本人の特性の理解
2つ目、本人の発達特性や性格特性についての見立てです。
生まれ持った特性として、どういったことがあるのか、も重要です。
もちろん、環境によってパーソナリティや考え方が構築されていく側面も大きいのですが、生まれ持ったものによって、どのくらい環境から影響を受けやすいか、も視点として必要かと思います。
幼少期の性格特性や、発達の偏りなどもわかっておくと、支援のヒントになると思います。
(育て方が難しい子どももいる。)
例えば、
昔どんな遊びが好きでしたか?
ご自身としては、どのような子供だったと思いますか?
お勉強のほうはどうでしたか?
中学、高校ではどのように過ごされていましたか?
・・・などなど。
話の流れに乗りつつ、聞いた情報のなかから、見立てていきます。
幼少のころから、現在の症状や問題に共通する点があったりもします。
3.病態水準の理解
初回面接だけではアセスメントするのは難しいかもしれませんが、病態水準の理解もとても大事です。
古典的なものですが、病態水準は以下の3つのレベルを見立てていきます。
・神経症圏(適応障害、軽症のうつ病、軽症の不安障害など)
・境界例(発達障害、人格障害)
・精神病圏(双極性障害、統合失調症)
もちろん、この診断があるからこのレベルだ!
とは言い切れませんが、ざっくりとした理解には役立つと思います。
(状況によって、病態水準が変動するとも思います。例えば、ストレスの負荷が高まると、一過性の精神病様症状がでたり・・・・など。)
基本的に患者さんはどの病態水準のレベルにいるかをわかっていると、アプロ―チも考えやすくなります。
例えば、神経症圏の患者さんでは、共感的なカウンセリングが効きやすかったり、
発達障害の患者さんでは構造化を強めたほうがよかったり、
精神病圏の患者さんでは、薬物療法が中心になってきたり・・・
(一概には言えませんが)
カウンセリングの方向性を選択してくためにも、必要な見立てかなと思います。
4.環境について
1,2,3では、発達や生活史など患者さん自身に焦点をあてていましたが、
現在の環境のなかでどのように困っているのか、も診ていきます。
問題が起こるときには、
患者さんがこれまで培ってきた対処方法では、乗り越えられない、という状況がほとんどだと思います。
基本的には、ご自身の対処のパターンは、育ってきた環境のなかで獲得されてきたものであり、固定化されていることが多いです。
患者さんに身についている対処と、現在の環境にどのようなギャップがあるのか理解するのが大事だと思います。
現在の環境について
・登場人物
・場所(職場?友人?恋人?)
・時間帯
・どのような問題が生じるか・・・
などを聞いていってみるとよいです。
5.まとめ
以上・・・
ざっくりとしたアセスメントの流れを書いてみました。
情報収集はもう少し緻密にやっていく必要があると思いますが、今回はひとまず、大きな流れについてを書いてみました。
基本的には1~4などの情報を踏まえていくと、どのように問題や症状が起こっているのか、結び付けて理解していきやすいかと思います(なかなか、経験がないときは難しかったですが^^;)。
やはり、臨床経験を積まないと、アセスメントの感覚もつかめないなと身をもって実感しています。
もしも今、まだケース数をこなせる現場ではない場合には、事例検討会を聞きに行ってみたり、事例集を読んでみたりするのもよいと思います。
私もまだまだ粗削りでアップデートの余地がたくさんあると思います。
初学者のかたの、少しでも参考になればと思います。
★雑談:しばらくブログを書いていないと、いい言葉が全然出てこないですね^^;説明がわかりづらかったら申し訳ないのですが、徐々にまたブログ筋を鍛えていこうと思うので、引き続きよろしくお願いします。